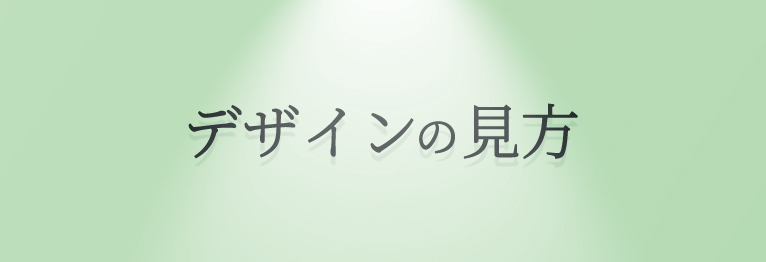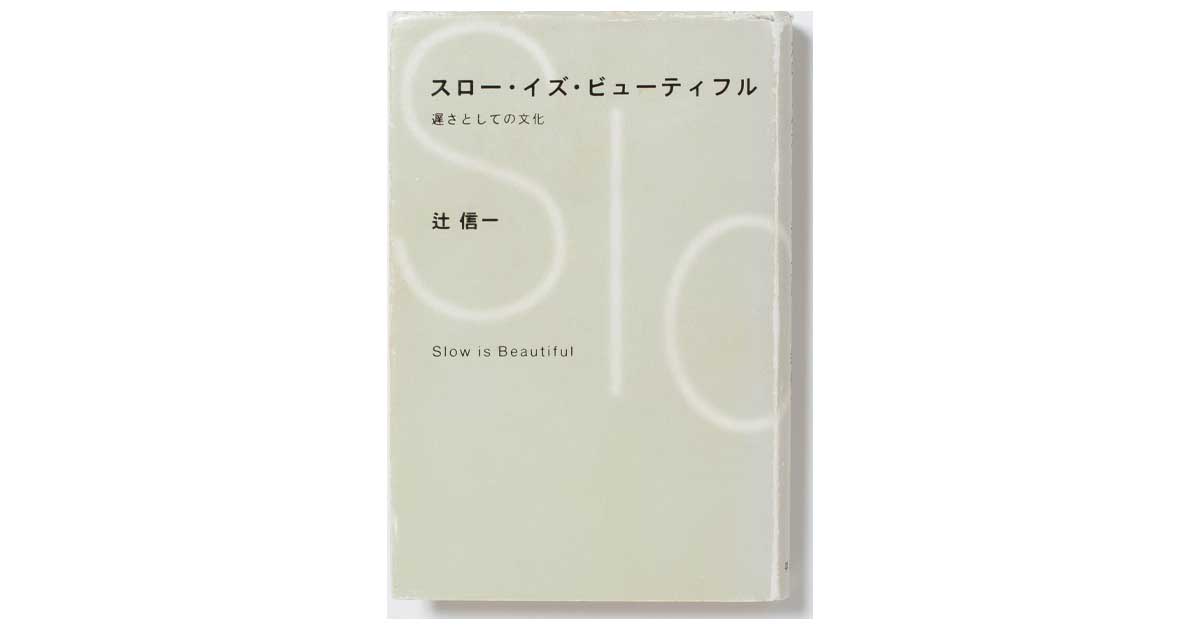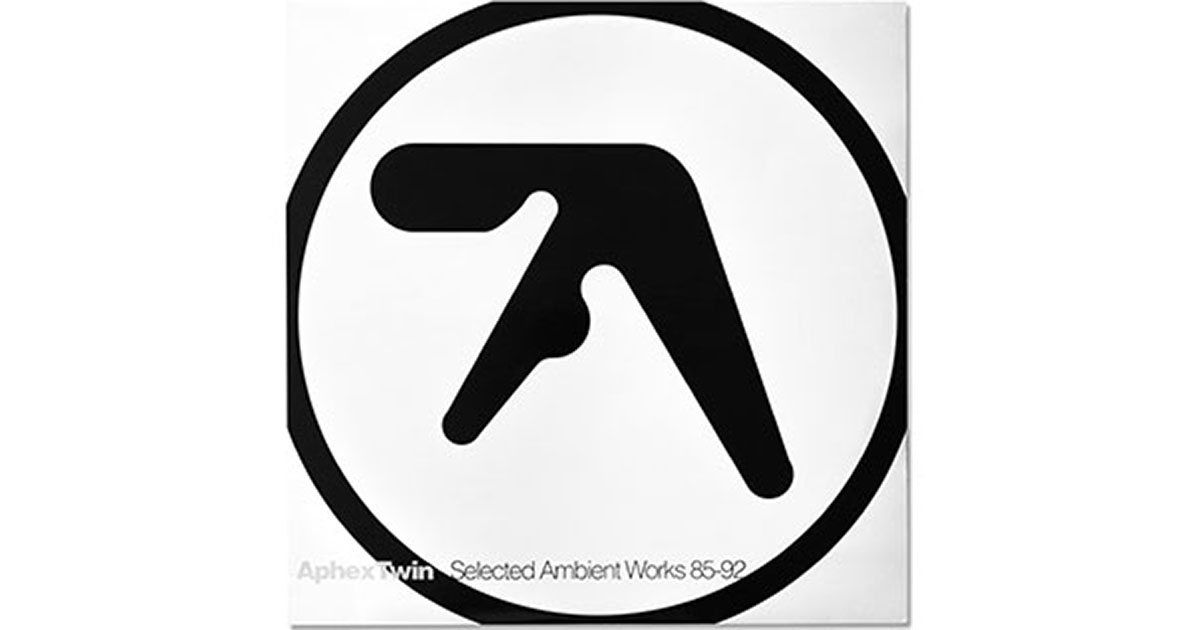小林さんが学生時代に手に入れた『江戸の遊び絵』。
大学の卒業制作に取りかかる頃、アイデアを探す過程で近代デザイン史以前の表現を模索している時期がありました。デザインという言葉が生まれる以前にも私たちが気付けていないだけの素晴らしい表現が大量に眠っているはず、また現在まで資料として残っているものは時代を問わずに疎通の測れる純度の高い表現なのではないかと仮定をして研究をしていました。
その頃出会ったのが、福田繁雄さんが監修を務めている『江戸の遊び絵』。この書籍の中で紹介されているものの中で特別に興味を持ったのが、山東京伝が木乃屑坊という芸名を名乗って制作したと言われている『新形紺名紋帳』。江戸中期の庶民文化を、紋とそれに付随する言葉で表現した黄表紙と言われる種類の書籍です。
当時、生活の中で触れる平面的な造形として最も一般的だった紋を、面白おかしく風刺をしたパロディ紋に置き換えて制作されており、さらにその上に皮肉たっぷりの言葉を添えることで紋というミニマルな造形の中から前後を想像できるように仕立て上げられている、ミニマルな風刺画が連続するような感覚が楽しめる書籍です。言葉は当時の言語ですが、紋の表現も相まって現代人である我々も時代を超えて当時の風俗を想像することができる点がとても面白く、見習うことができる思考だと思いました。
これら古く優れた表現を自分なりの方法でなんとか紹介しようと思い、近代デザイン史以前の表現のリメイクプロジェクトとして卒業制作では明治初期に編纂された正倉院御物の記録図譜を...