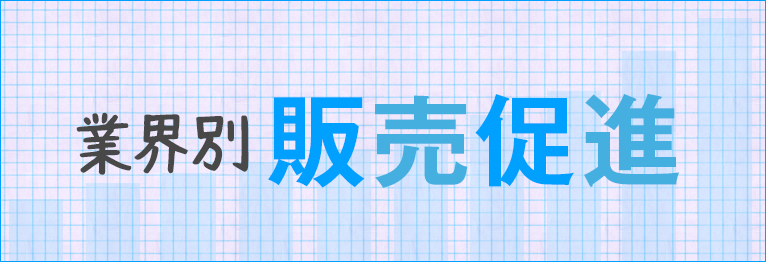コンビニのカウンターコーヒーが好調な一方で、コーヒー豆や抽出方法にこだわるスペシャリティコーヒーブームが脚光を浴びるなか、新たな価値提供を目指す新業態のカフェが続々と登場している。新業態におけるコンセプト開発、店づくり、人をひきつける仕掛けを通して、カフェ業態の可能性を探る。
コーヒーを一杯ずつハンドドリップする、昔ながらの日本の喫茶文化が見直されている。とはいえ、古くからある喫茶店は常連客が多くて入りにくい、と感じる人も多いだろう。そこで最近注目されているのが、伝統的な喫茶文化を取り入れながら、親しみやすさと居心地のよさを高めた、新しいタイプのカフェである。大人が楽しめる飲み物や食事を提供し、人と人とがゆるやかにつながれる場としての役割も期待される。
新たなカフェ需要の創出を狙い、新業態を展開する4社を取材した。
[CLOSE-UP! (1)]
すかいらーくグループ
むさしの森珈琲
長居したくなるカフェ

「高原リゾートの珈琲店」をイメージしたデザイン。「プレミアムテラスコーナー」(左)や、高原ホテルのラウンジをイメージした「ラウンジコーナー」(右上)など4つのゾーンに分かれている。一人でもゆったりくつろげるよう、雑誌も豊富に取り揃えている(中央下)。
わくわくするメニューや盛り付け

エッグベネディクトやフローズンドリンクなど、流行りのメニューをいち早く取り入れている。運ばれてきた瞬間にテンションが上がるような盛り付けを意識。

看板商品「ふわっとろパンケーキ」。食後のデザートに追加注文しやすいよう580円という手頃な価格にし、誰かとシェアできるよう2枚セットで提供。
話題の最新メニューが手軽に味わえる郊外型カフェ
すかいらーくグループ
3月7日にオープンしたばかりのロードサイドカフェ「むさしの森珈琲」(横浜市南区六ツ川)。高原リゾートをイメージした広々とした店内では、平日は朝7時の開店からシニア客がモーニングを楽しむ姿が見られる。
同店のメニューは、“なんでもあり”が売り。オリジナルの看板商品「ふわっとろパンケーキ」から、「エッグベネディクト」などのセレブ風朝食、モーニングタイムにはドリンク注文でゆで卵とトーストが無料でつく名古屋の喫茶店風サービスまで、幅広い食事ニーズにフルサービスで応える。同店を運営するすかいらーくグループのニラックス・マーケティンググループディレクター 久保木 稔氏は、「市場が伸びているモーニング需要を取り込むため、誰でも楽しめるメニューづくりを目指しています」と話す。
10時を過ぎると女性客が増え、この時間帯から夕方までほぼ満席の状態が続く。「子どもを保育園や学校に送り出した母親たちが、ママ友と一緒にくつろぎながら会話と食事を楽しまれるケースが多い」と久保木氏。休日ともなれば、朝7時半頃にはシニア客や家族連れで満席になるほどの繁盛ぶりだという。
むさしの森珈琲は、すかいらーくグループ初のカフェ業態である。同グループは現在、洋食や和食、イタリアン、焼き肉など10ブランド、約3000店舗を展開。「グループ全体の成長戦略を描くうえで、成長が見込めるカフェに着目して新業態を開発しました」と久保木氏は話す。
1号店は、おはしCaféガスト六ツ川店からのブランド転換である。同店の半径3キロ圏内には、グループの既存ブランド10店舗が立地する。そのようななかで、「既存ブランドとは異なる新たな客層を開拓し、エリア全体の売り上げを伸ばすことがカフェ業態の使命」と久保木氏。狙うのは、フルサービスのカフェでゆったりとした時間を楽しみたい30~50代女性とシニア層である。
グループのファミレス業態に比べてメニュー数を絞り込み、1品ずつ手間をかけることでクオリティを高めた。注文ごとにメレンゲを立てて焼き上げる「ふわっとろパンケーキ」は、「他では味わうことのできない食感を目指して1年かけて開発した」(久保木氏)。また、メイソンジャーに入れたフローズンドリンクや、ヘルシースムージーなどの“流行りもの”もいち早く取り入れている。コーヒーはレインフォレスト・アライアンス認証農園産豆を使用したブレンドに加え、単一豆をハンドドリップしたスペシャリティコーヒーも用意した。
「情報に敏感な女性のお客さまが、運ばれてきた食事を見て『かわいい!』『おしゃれ!』とテンションが上がるような食材や盛り付けを意識しています。青山や表参道のカフェに行かなくても、流行のメニューが近所で楽しめる。そんなカフェを目指し、新たな需要を創出していきたい」と久保木氏は意気込む。
長時間の滞在でもう1品注文してもらう工夫
店内は、木のぬくもりが感じられる内装で、くつろぎと癒しが感じられる空間にした。その日の気分やシーンによって使い分けられるよう、テーマに沿った4つのゾーンを設けた。居心地の良さを追求した結果、平均滞在時間は1.5~2時間と、既存ブランドの約1時間に比べてかなり長い。
長居する客が増えると回転率が落ち、収益減が懸念されるところだが、同店は116席という十分な客席を確保し、客数を増やすことで収益力向上を狙う。加えて、客単価を上げるため、パスタやドリアなどの食事とコーヒーを注文した後に、パンケーキなどのデザートも食べてもらえるようメニューに工夫を凝らす。例えば、「ふわっとろパンケーキ」を580円という手頃な価格設定にし、さらに誰かとシェアできるよう2枚セットにすることで、追加注文しやすくしているのだ。
同店の平均客単価は1000円程度だが、ランチ時にはさらにアップする。一般的にファミレス業態では、ランチ時はお得なセットなどが好まれ客単価が下がる傾向にあるというが、同店では居心地のよさとメニューの工夫により、滞在時間に比例して注文が増え、客単価を押し上げるという好循環を生み出している。
1号店がオープンして約1カ月。おはしCaféガスト時代に比べて売り上げは倍増し、好調なスタートだ。1号店が新たな客層を開拓し、従来のおはしCaféガスト利用者が近隣の既存店を利用するようになったことで、近隣の既存店の売り上げも伸びているという。「カフェの需要が予想以上にあることがわかり、手ごたえを感じている」と久保木氏。すかいらーくグループは、今後もエリア内収益の最大化を念頭に、ブランド転換を含むカフェ業態の出店を進め、16年までに40~50店の出店を目指す。
家の近所で立ち寄れる“スタバ” 人と人が気軽につながる場に
スターバックス コーヒー ジャパン
東京・下北沢の住宅街に立地する「インスパイアード バイ スターバックス 代沢5丁目店」。入口にスターバックスの緑色のロゴマークは見当たらず、一見するだけではスターバックスの店舗だとは気付きにくい。ある平日の16時過ぎに店を訪れると、近隣住民らしき人たちやママ友グループ、学生やスーツ姿のビジネスマンらで混雑していた。とはいえ喧騒さはなく、低めのソファや椅子がゆったりと置かれた店内には、自宅リビングのような居心地の良さが漂う。
この店は、スターバックス コーヒージャパンが住宅地に展開する新業態「インスパイアード バイ スターバックス」の2号店で、13年11月にオープン。新業態は都内に3店舗ある。同社はこれまで、繁華街やビジネス街などの商業地に出店してきたが、「家の近所にもスターバックスのようなカフェがほしい、という声に応えて、住宅地に合った新業態を開発しました」と同社戦略&業態開発部部長の山田英輔氏は話す。
“Your Neighborhood and Coffee”をコンセプトに、自宅の延長のようなリラックスした空間で、ひと手間かけたこだわりのコーヒーや食べ物をセルフサービスで提供する。繁華街の店舗ではサービスの効率やスピードが重視されるのに対し、主婦やシニア層など近隣住民が多く利用する住宅地の店舗では、快適にくつろぎたいというニーズに応えたものだ。
コーヒーは、豆の種類だけでなく、抽出方法を選ぶことができるほか、バリスタによるラテアートも楽しめる。他にも、アイスなのにミルクが泡立つ「アイスフォーム マキアート」や、手作り感あるリンゴの果肉が特徴の「マムズ アップル&ティー」など、他では味わえないオリジナルメニューも開発した。
通常の店舗では珍しいキッチンまわりのカウンター席も、一人客にもカフェの時間を楽しんでもらおうと設けている。カウンター席に座れば、バリスタがドリンクを一杯ずつ手づくりする様子を眺められるほか、バリスタにコーヒー豆の選び方について教えてもらうこともできる。「通常の店舗ではお客さまとのコミュニケーションに制約がありますが、ゆったり過ごしていただけるこの店だからこそ、バリスタとの会話を通じて当社こだわりのコーヒーにも興味を持っていただければと思います」(山田氏)
新業態ではまた、アルコールも提供している。同社発祥の地であるアメリカ・シアトルのビールや日本の地ビール、同社のコーヒースペシャリストが選んだワインなど、スターバックスならではの品揃えを意識。お酒と一緒に小腹を満たせるサイドメニューは女性にも好評だという。「夜に一人で来店し、ワイン片手に読書して過ごす30代くらいの女性客もいらっしゃいます。お酒を飲むことが目的というより、夜一人でくつろぎたい人にとって、カフェでの“ちょい飲み”はニーズがあると感じます」(山田氏)
友達の家に遊びに来たような親しみやすい空間づくり
住宅地に立地するカフェの場合、いかに地域に溶け込めるかが成否を握ると山田氏は言う。商業地に比べて集客が弱い住宅地では、常連客に頻繁に通ってもらう必要がある。同社では店舗の従業員を「パートナー」と呼ぶが、地域に溶け込むためにパートナーと利用客、店と地域のつながりを大事にしている。
レジカウンターを通常より低めに作ったり、カウンター内で働くパートナーの姿がよく見えるオープンな作りにしているのも、パートナーと客の心理的な距離を縮めるための工夫である。パートナーはユニフォームを着用せず、私服におそろいのエプロンを付けることで、「友達の家に遊びに来たような親しみやすさを感じてもらえれば」と山田氏。また、店を地域の人が集まる場にしようと、ヨガ教室やビールセミナーなどのイベントを不定期に開催するほか、近隣に住むアーティストの写真や絵を店内に展示し、作品紹介の場として活用してもらっている …