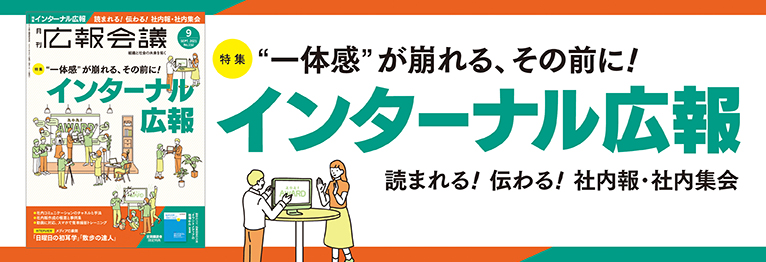リモートワークの浸透でインターナルコミュニケーションの在り様が変わってきている。そのひとつが社内報だ。マンネリを打破し、いかに関心を持って見てもらうか。その実態を編集部が探った。
コロナでテレワークが当たり前となった今、社内報は「紙」「ウェブ」といった形のみならず、その意義も変化している。それは、散り散りとなった社員の「心の拠り所」となる社内報が求められている、ということだ。
不安を募らせる社員。中でも新卒に焦点を当て、取り組んだ企業がある。「新入社員は、先輩はもちろん、同期の顔や名前も分からず、おそらく一番不安を抱えて働いていた世代。そこで、彼らをゲストに、抱えている不安や仕事の工夫などを動画で発信。『自分だけが悩んでいるんじゃないとわかり、安心した』という声につながりました』」(人材サービス)。
あえて紙、という声も
じっくり読んでもらい、態度変容を促したい。そうした観点から、ウェブではなくあえて紙を選ぶ企業も。「コロナ下で働く社員に対する、社長からの感謝のメッセージを社内報に掲載。冊子なので閲覧率が上がったわけではないですが、良い誌面になりました。また、社長のインタビュー記事には多くの社員から感動的なコメントが寄せられました」(IT・情報通信)。「ウェブではなく紙媒体だからこそ自宅にも持ち帰ることができ、じっくり読んでもらえていると考える(期待する)」(建設・建築)。
その他、周年事業にはやはり紙、との声も。「3周年記念誌の作成に力を入れています。直近はウェブコンテンツに振り切っていましたが、3周年誌は紙媒体を選択しました」(IT・情報通信)。コロナといえど、コンテンツの目的や対象によって柔軟に手段を選択する必要があると考えているようだ。
マンネリ化は今も課題に
一方で、紙・ウェブ関係なく課題なのが中身のマンネリ化。「社内報自体は30年毎月発行していますが、配付しても読まれていないのでは、ということが課題でした」(電機・精密機器)。そこで、同社は社内報に関しアンケートを取り、結果を分析。対象を絞った企画を立てるようにして、マンネリ化を防いだという。
また、「音声」という第三の選択肢で新規性を打ち出した企業も。「当社では、2021年4月より音声コンテンツの公開を開始しました。工夫したのが、そのままLive配信するのではなく、収録後10分程度に編集して展開。長いと全部聞いてもらえないので、10分程度に絞りました。仕事をしながら隙間時間に聴けるということでリピートして聞いてくれています」(広告・メディア・報道機関)。
また、「他の社員からの信頼が厚い社員や、コアな社員、応援したいと周りに思われている社員を積極的に取り上げると反応が違うなというのを改めて感じます。より興味を持ってもらうには、人選は大事だと実感しました」(同)。
仮に新しいツールを導入しても、その目新しさから、一時的に...