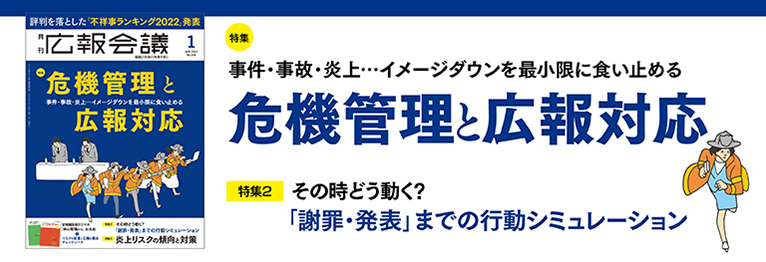大量転職時代となり、リスクとして高まっているのが営業秘密の流出だ。こうした事件においては、企業vs企業の構図が生まれ、広報活動の瞬発力・説得力の違いが企業イメージを左右すると筆者は指摘する。
2022年の企業不祥事では、上級幹部がライバル会社に転職し、社長に就任したあと、古巣の会社から刑事告訴され、逮捕されるという驚天動地の事案があった。告訴の理由は、会社の営業秘密を持ち出し、移籍後の会社の経営に不正に利用したから。
管理職・経営層の転職が増える中、こうしたリスクを回避するには、企業間の移動を大前提にルールを設け、幹部社員との間に適正な契約をしっかり結ぶことが必要である。そのうえで、万一問題が生じた際、可及的速やかに自社の取り組みを説明することが重要である。広報対応の巧拙が企業のレピュテーションを分ける可能性もある。
営業秘密に当たるのは
回転寿司チェーン4位の「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイトの田邊公己社長(当時)が9月30日、不正競争防止法違反の容疑で逮捕された。回転寿司3位である「はま寿司」を傘下に持つゼンショーホールディングスから転職した際、前職の営業秘密を持ち出し、新職場「かっぱ寿司」の経営に不正に利用したとの容疑である。
一般的に、営業秘密は、①秘密として管理されている、②生産・販売・その他事業活動に有用である、③公然とは知られていない──の3要件を満たす必要があり、ここ数年ニュースで話題になった営業秘密流出案件は、技術情報や顧客・取引先情報が多い(図参照)。
注 各種報道からのまとめ。文責筆者
今回持ち出したとされる情報は、仕入れ関連データ(食材、仕入先、仕入れ価格など)。容疑者は逮捕前の任意聴取で、情報の持ち出しを認めたうえで「大した内容ではない」などと話していた(2022年10月1日時事ドットコム)そうなので、3要件の②「有用性」を満たさず、営業秘密には当たらないと踏んでいた可能性がある。
実際、「はま寿司」側から2021年4月に刑事告訴され、同年6月末には自宅と勤務先(転職先のカッパ・クリエイト)が警視庁に家宅捜索されたにもかかわらず、その後、1年半もの間、運営会社の社長職に留まり続けた。この点は、東証プライム市場上場企業のガバナンスとして疑問符をつけざるを得ないだろう。
民間企業の社内調査に限界があり、調査対象が社長というむずかしさがあるにせよ、パスワード管理されている情報を、転職前の元部下を使って取得したことが判明した時点で、社長解任をするのが...