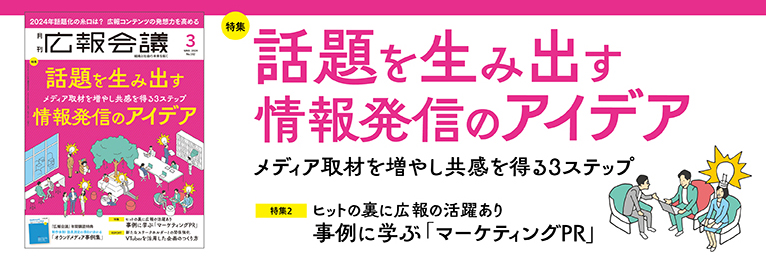社会課題となっている「人手不足」にメディアからの関心も高まる中、「働く場」としての企業の魅力を伝えていく広報が重要になっている。従業員、求職者にとっても重要な情報をいかに発信し、コミュニケーションしていくか、語り合った。
働き方に関する広報が変化
これまで
社内制度をはじめ「働く場」としての企業についての情報発信は、メディア向けにニュースバリューのある形で発信するというよりは、採用広報や社内広報向けに留まりがち。
これから
社会課題である人材不足に関連した新制度や、業界を先駆けた取り組みにメディアも注目。その取り組みの意図や背景を社内外にしっかりと伝えることが重要に。
業界を先駆けメディアが注目
─働き方に関する施策の広報で反響が大きかったものを教えてください。
瀧上:スター食堂は、京都を拠点に飲食店を展開し、2025年に創業100周年を迎えます。飲食業では営業時間に伴う長時間労働の常態化や公休の取得の難しさが課題となっています。
そこで私たちは2023年夏、週休3日制の導入を発表しました。メリハリの利いた週休3日制を打ち出していて、休日を増やす一方で、所定労働時間を8時間ではなく10時間に設定し開店から閉店まで働くスタイルです。希望に応じて働き方を選べるようにもしています。週休2日制では、営業時間より早く帰宅したり、時短日をつくったりと、シフトのやりくりが煩雑になっていました。できるだけシンプルにして、店長や料理長の負担を減らすために週休3日制の導入を決めたという背景があります。
なぜ取り組むのかを繰り返し社内外に伝えていくことが大事

スター食堂「週休3日制」
常態化している飲食業の長時間労働を変えるべく、老舗のスター食堂が週休3日制を導入。プレスリリースでは、導入の狙いや業界の課題、同社のこれまでの取り組みを振り返りながら、業界の当たり前を打ち破り「より豊かな選択肢」を用意したいという思いを綴った。

プレスリリースでは、働く社員のビジュアルも多数掲載した。
土屋:日本交通では、東京と大阪を中心に全国で約9000台のタクシー及びハイヤーを展開しています。運送業界では「人材確保」が大きな課題です。タクシー業界で言うと、都内法人タクシー乗務員の平均年齢は58歳くらい。コロナ禍では乗務員が約2割減少しその状態のままコロナが明け、エリアや時間帯によっては需給バランスが崩れている状態が発生しています。事業者として「働きやすい環境」の構築に努めているところです。
当社では2012年から乗務員の新卒採用に取り組んでいて、2020年に開設した葛西営業所は、所属乗務員がすべて新卒採用者で構成されています。タクシー乗務員は営業中1人で業務を行うので従業員間のコミュニケーション不足やキャリア構築支援、モチベーション維持は課題になります。
そこで2023年2月、同営業所が移転リニューアルするのに伴い、タクシー乗務員が自ら運営する社員向けカフェを営業所内に設置。カフェのコンセプト、メニュー、レイアウト設計、関係業者との折衝などは新卒社員自らが主体的に行っており、新卒乗務員の育成に注力していることを発信しました。
社外での反響を社内にフィードバックすることで良い循環を生む

日本交通「新卒社員による自主運営カフェ」
新卒採用を積極的に行ってきた日本交通には、所属する乗務員が全員新卒の営業所があり、2階に社員向けカフェを設けた。従業員間のコミュニケーション不足の解消・新しいキャリアモデルの構築が目的。カフェのコンセプトづくりから調理・販売まで新卒採用者が行い、メディアにもその様子を公開した。

気軽な交流ができる場として活用されているカフェ。
芝:りそなホールディングスは、りそな銀行等の金融持株会社です。信用第一の業界ゆえの規制や硬さもある一方で、異業種の参入も進んでいます。世の中が変わり、多様性が重んじられている中で、従業員の服装に対する価値観を尊重し、より自由な発想でパーパスに掲げる「金融+で、未来をプラスに。」を実践していくことを目的として、2023年10月25日に服装自由化を発表し11月1日から全店で実施しています。もともとは取引先にベンチャー企業が多い支店から「服装を自由化したい」という発信があり実現した施策です。従業員の自律性を高めることにつながるのではとの思いも導入の後押しとなりました。
関係部署の意図を腹落ちさせメディア対応しミスリードを防ぐ

りそなホールディングス「服装の自由化」
りそなグループでは「スーツやネクタイ着用等のフォーマルな服装で業務にあたる」というルールを全拠点で廃止。社会の価値観が多様化するなかで、画一的に服装を定めるスタイルから脱却し、従業員が自律的に相手や場所に合わせた服装を着用することを目指す。