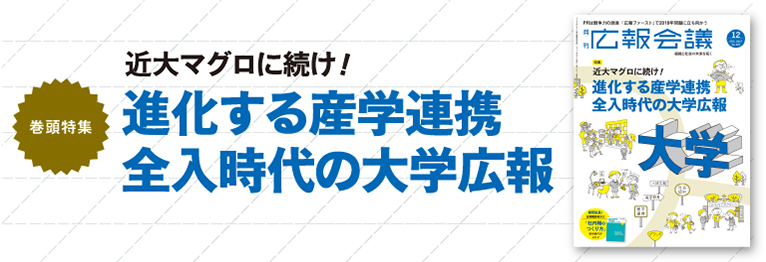1996年、東洋大学がムーミンを起用した当時の広報を統括していたのが、現在は女子栄養大学の常務理事で"レジェンド"とも呼ばれる染谷忠彦氏だ。秋田県の国際教養大学のアドバイザーも設立時から務めている。

年間のメディア露出 約400件
カネテツデリカフーズ(神戸市)との産学連携包括協力に関する調印式での学生プレゼン(2017年2月)。
大学広報は、学内にある「宝物」を売るところ。ある意味、営業部隊なんです。かつて東洋大学の入試部長を務めていた1999年当時、「大学の入試部門は営業部隊」と日経新聞で取り上げてもらったこともあります。
一番の宝物は、教員が学生を育てていく「教育力」。いい教育がなければ「就職力」で売ることもできません。だから流行に乗って目新しい学部を新設しても、建学の理念や世間のイメージに反した学部・学科では意味がない。学生は学びの手応えがなく実績も出ません。数年で廃れてしまいます。
その点、2004年の設立時からアドバイザーとして関わってきた秋田県の公立大学である国際教養大は、教育面の強みが突出していました。地方の山奥にありながら、すべて英語の講義で日本の大学にはない強みがある。これはいけると思い、私立大学と同じ土俵で戦うための提案を続けています。
2003年から広報を統括している女子栄養大学はかつて、地方での認知がまったくない大学でした。管理栄養士の国家試験で毎年100%近い合格実績がありながら、イメージは地味で暗い。キャンパスも都心から50キロ離れています。市場としての高校での認知は3年、社会的な認知には7年かかるだろうと予測していました。
そこで仕掛けたのが、本学の創立者・香川綾が戦後日本で初めて考案した計量カップなどをキャラクター化して広めること。自前で栄養にこだわって運営している学食も珍しいので、取材を誘致してレシピ本も出版しました。ちなみに同時期にレシピ本が流行ったタニタで社員食堂の栄養士として活躍しているのも、本学の卒業生です。
産官学連携の事例も増えていて、企業や行政、高校などと約150件の案件が動いています。例えば卒業生を生涯学習講師として高校に派遣して「栄養学」について講義をする場は、3年間で約450件に達しました。部活動の食のサポートにも取り組んでいて、高校のほか古巣の東洋大学駅伝チームも支援しています。「食べることも大切なトレーニング」と位置づけ、選手の体調管理、栄養面のサポートを継続して行うことが、好成績を続ける理由のひとつになっていると思われます。
企業とはイオンなど流通とのお弁当の共同開発、食品メーカーとのコラボ商品開発などが多いですね。社員食堂のメニューを監修するケースもあります。これらの取り組みによって、年間で400~500件のメディア露出を確保することにつながっています。
大学は「職員力」こそが大事です。広報も含めて、若い人材を採用して育ててほしい。理念を理解して、大学を知り尽くした人材がリーダーシップをとってほしいですね。大学広報の理念は「他大学ではできない広報活動を行うこと」ですが、大学職員だけでは限界があります。他大学の動向も参考にしながら、一般の企業の広報戦略から学べることが多くあると思います。(談)

産官学連携 150件
2009年から上西一弘教授(栄養生理学研究室)が、東洋大学駅伝チームの栄養サポートを開始。2015年には保護者会有志応援団を結成し、両校名が入った手旗などを持参し応援に駆け付けている。

女子栄養大学 常務理事
染谷忠彦(そめや・ただひこ)氏
1965年東洋大学経済学部卒業後、大学運営に携わり、入試部長として他大学に先駆けた入試戦略と斬新な広報活動を展開。2003年女子栄養大学広報部長兼理事長付部長に就任。現在、常務理事。2004年4月開学の国際教養大学立ち上げから現在までアドバイザーも務める。